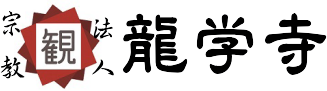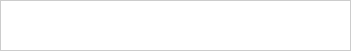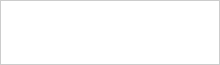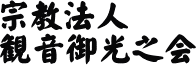道元(どうげん)和尚は、鎌倉時代初期の禅僧で、日本における曹洞宗(そうとうしゅう)の開祖として知られています。その思想は仏教界だけでなく、哲学や現代思想にも大きな影響を与え続けています。
プロフィール概要
- 生没年: 正治2年(1200年)〜建長5年(1253年)
- 出自: 京都の公家である久我家に生まれ、幼名を「文殊丸(もんじゅまる)」と言います。幼くして父を、8歳で母を亡くし、無常(むじょう)の世に強い関心を抱きました。
- 宗派: 曹洞宗
- 主な著作: 『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)』
- 開山した寺院: 永平寺(えいへいじ、福井県)
生涯と教え
道元和尚の生涯は、真実の仏道を求めてひたすらに修行と探求を続けた道程でした。
1. 出家と比叡山での問い
14歳で比叡山(ひえいざん)にて天台宗の僧侶となりましたが、「人は皆、仏になる資質(仏性)を持っていると教えられているのに、なぜ修行をしなければならないのか?」という根本的な疑問を抱き、その答えを得ることができませんでした。この問いは、道元のその後の人生を決定づけるものとなりました。
2. 栄西との出会いと入宋
比叡山を離れた道元は、京都の建仁寺(けんにんじ)で、日本に臨済宗を伝えた栄西(えいさい)に師事し、禅の教えに触れました。その後、栄西の弟子である明全(みょうぜん)と共に、24歳で本場の禅を学ぶために中国(当時の宋)に渡ります。
3. 如浄との出会いと悟り
中国の天童山(てんどうざん)で、曹洞宗の僧侶である天童如浄(てんどうにょじょう)に出会います。如浄から「身心脱落(しんじんだつらく)」という言葉を聞き、深い悟りを得たとされています。この「身心脱落」とは、体と心にまつわるすべてのこだわりやとらわれから解放されることを意味します。この体験から、道元は「只管打坐(しかんたざ)」、すなわち「ただひたすらに坐禅をする」という、悟りそのものとしての坐禅の教えを確立しました。
4. 帰国と永平寺の開山
28歳で日本に帰国した道元は、まず京都で教えを広めましたが、旧仏教勢力からの圧力により、越前国(現在の福井県)に移ります。そして、寛元2年(1244年)に、大仏寺という修行道場を建立しました。これが後に永平寺と改称され、日本曹洞宗の根本道場となりました。
5. 主な著作『正法眼蔵』
永平寺を中心に活動する傍ら、道元の思想を集大成した大著**『正法眼蔵』の執筆に励みました。この書は、仏教の教えを道元自身の視点で深く解説したもので、「仏道をならうというは、自己をならうなり。自己をならうというは、自己をわするるなり」という有名な言葉に象徴されるように、坐禅を中心とした自己探求の重要性を説いています。
道元和尚の思想的特徴
道元の教えは、「仏教の本質は坐禅にあり」という点に集約されます。
- 只管打坐(しかんたざ): 坐禅を悟りのための手段ではなく、坐禅そのものが仏の姿であり、悟りであると説きました。
- 修証一等(しゅしょういっとう): 修行と悟りは、時間的に二つのものではなく、一つのものであるという考え方。修行をすることが、すでに悟りの姿であると教えました。
- 日常生活のすべてが修行: 坐禅だけでなく、食事、清掃、睡眠など、日常生活のすべての行いが仏道修行であると説き、修行僧の生活規範(清規)を確立しました。
道元和尚は、享年54歳でその生涯を閉じましたが、彼の残した教えと『正法眼蔵』は、後世に大きな影響を与え、現代にまで引き継がれています。